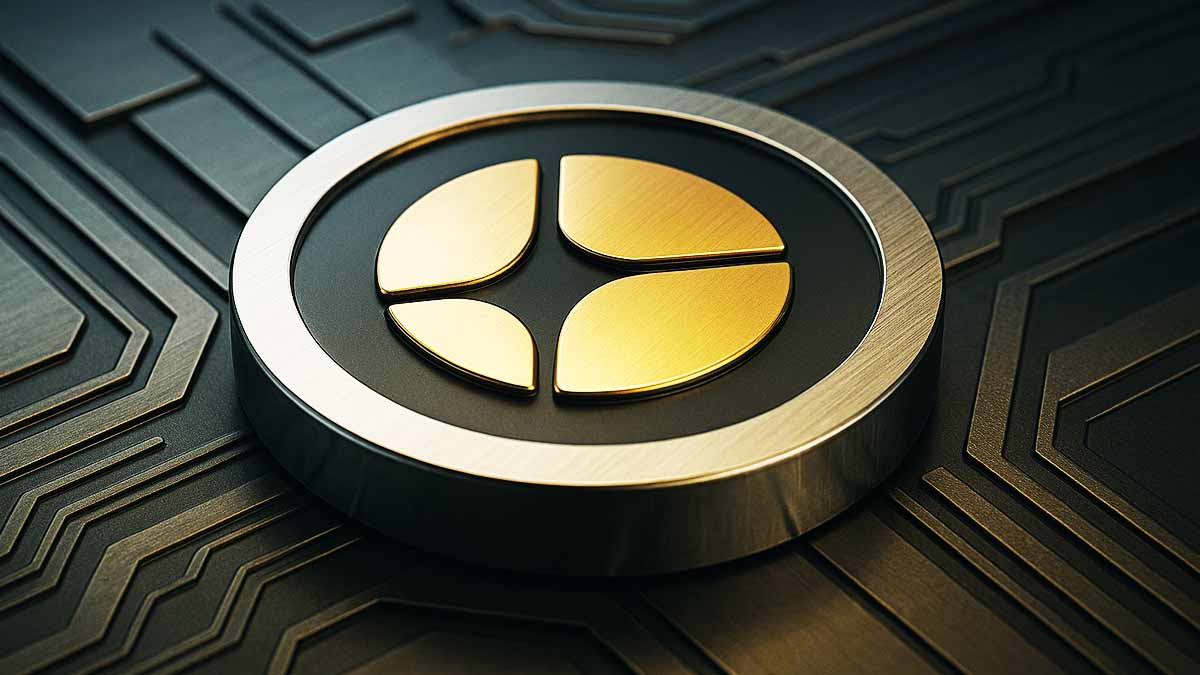ステーキングとは対応する仮想通貨を保有してブロックチェーンネットワークの運営に協力し、その報酬として仮想通貨を受け取る仕組みです。
2022年のイーサリアム大型アップデート以降に注目が高まり、2025年現在では国内外で様々なサービスが提供されています。
この記事では「仮想通貨(暗号資産)ステーキングとは何か」からメリット・デメリット、具体的な始め方、2025年おすすめの銘柄・サービス、そして最新動向や規制状況、よくある質問まで徹底的にわかりやすく解説します。
初心者はもちろん中級者にとっても役立つ情報を網羅していますので、ぜひ参考にしてください。
こちらから読む:ステーキング関連の記事を新着順で確認「ステーキング」関連ニュース
仮想通貨ステーキングとは?
ステーキングとは、仮想通貨のプルーフ・オブ・ステーク(PoS)という合意形成アルゴリズムに基づくネットワークで、対象通貨をブロックチェーン上に一定期間預ける(ロックする)ことでネットワーク維持に貢献し、その対価として報酬が得られる仕組みです。
簡単に言えば、対応する仮想通貨を「持っているだけで増やす」ことができるサービスです。値上がり益を狙って保有するだけでなく、ステーキングを活用することで長期保有中にも利息のようなリターンが得られるため、近年人気が高まっています。
ステーキングで得られる報酬は、預けた仮想通貨と同じ銘柄で支払われることが一般的です(例:ADAをステーキングすると報酬もADAで受け取る)。報酬利率はネットワークの設計や参加者数によって異なりますが、おおむね年率数%から10%前後が多く、中には10%以上の高利回りを実現する通貨もあります。
銀行預金(金利0.001%程度)と比べても圧倒的に高い利率が期待できるため、「暗号資産を増やす新たな手段」として注目を集めています。
なお、ステーキングはマイニング(採掘)とは異なる仕組みです。ビットコインなどのマイニングは高性能な計算機で複雑な計算を競う必要がありますが、ステーキングでは基本的に通貨を保有・ロックするだけで参加できます。専門的な機材は不要で電力消費も格段に少なく、より手軽かつ環境に優しい仕組みと言われます。
ステーキングの仕組み(PoSの概要)
仮想通貨のステーキングは、ブロックチェーンのコンセンサスアルゴリズムである「プルーフ・オブ・ステーク(PoS)」によって成り立っています。PoSネットワークでは、コインの保有量やロック期間に応じてブロックの承認者(バリデーター)が選出され、取引の検証・ブロック生成が行われます。
ステーキング参加者は自らバリデーターとしてネットワーク運用に直接参加するか、もしくは自分の保有コインを信頼できるバリデーターに委任(デリゲート)することで間接的に参加します。
バリデーターが新しいブロックを生成すると、取引手数料や新規発行コインからなるブロック報酬が与えられ、その一部がステーキング参加者に分配される仕組みです。 要するに、PoS型の仮想通貨では「たくさんコインを持っている人」がネットワーク承認に大きく関与し、その見返りに報酬を得る構造になっています。
参加者は自分の資産をロックすることでネットワークのセキュリティ向上に貢献し、報酬としてコインを追加で受け取ります。例えばイーサリアム(ETH)の場合、ステーキングに最低32ETHが必要で、自身でバリデータノードを運用すると定期的にETH報酬が得られます。
また、一般ユーザーは取引所やプールを通じて少額から委任参加できるため、PoSでは参加ハードルが低く多くの人が分散的にネットワーク維持に関われる点が特徴です。
なお、ビットコイン(BTC)はPoSではなくPoW(プルーフ・オブ・ワーク)のため、厳密には「ステーキング」はできません(ビットコインを預けて利息を得るサービスはありますが、それは後述するレンディングであり、ブロックチェーン上のステーキングとは異なります)。
ステーキングのメリット・デメリット
仮想通貨ステーキングにはさまざまな利点がある一方、注意すべきリスクや欠点も存在します。ここではステーキング全般のメリット・デメリットを整理します。
ステーキングのメリット(利点)
- 保有するだけで報酬が得られる
相場の売買タイミングを気にせず、長期保有中に自動で暗号資産を増やすことができます。銀行預金の利子より高いリターンが期待でき、手間なく資産運用できる点が魅力です。 - 専門知識や設備が不要
マイニングのような高度な機材や難しい設定は基本的に必要ありません。取引所を利用する場合は口座に対象通貨を入れておくだけで始められ、初心者でも簡単です。 - ネットワークの安定に貢献できる
ステーキング参加はブロックチェーンのセキュリティ強化につながります。単に利益を得るだけでなく、応援するプロジェクトのネットワーク維持に協力できる点もメリットです。 - 複利運用が可能
得られた報酬をさらにステーキングに回すことで、雪だるま式にリターンを増やすことができます。報酬受取と再ステークを繰り返せば、長期的に見て資産の成長スピードを高められます。 - 自己管理でセキュリティ向上
(※自分で公式ウォレットを用いる場合)取引所など第三者に預けず自分のウォレットで管理できるため、ハッキング被害や取引所破綻リスクから資産を守りながら運用できます。公式提供のウォレットを使えば信頼性も高く、安全に保管しつつ増やせます。
ステーキングのデメリット(注意点・リスク)
- 価格変動リスク
ステーキング中でも元本である仮想通貨の市場価格は変動します。価格下落によって評価額が減少するリスクは常にあります。年利5%でコイン枚数が増えても、価格が50%以上下落すれば円換算の総資産は減ってしまいます。 - 流動性リスク(ロック期間)
多くのステーキングでは一定期間コインがロック(拘束)されます。一度ステーキングすると、解除までそのコインを売却・移動できない場合があり、急な資金需要や相場変動に対応しづらいです。サービスによっては途中解除可能なもの(柔軟型)もありますが、基本的に流動性が下がる点に注意が必要です。 - サービス提供者への依存
取引所など第三者サービスを利用する場合、その業者の信用リスクが伴います。取引所がハッキング被害に遭ったり経営破綻したりすると、預けた資産が引き出せなくなる可能性があります。信頼性の高い事業者を選ぶことが重要です。 - スラッシングリスク
一部のPoS通貨では、バリデーターが不正を行ったり長時間オフラインになるとペナルティ(スラッシング)でステークしたコインの一部が没収されることがあります。通常、信頼できるバリデーターに委任すれば滅多に起こりませんが、ネットワーク特有のリスクとして知っておきましょう。 - 報酬利率の変動
ステーキングの年利は固定ではなく、ネットワークの状況により変動します。参加者が増えると一人当たりの報酬が減る傾向があり、逆にネットワーク利用が増えると手数料収入が増えて利率が上がることもあります。開始時に聞いていた利率が将来も続く保証はないため、最新情報の確認が必要です。 - 税金・確定申告の義務
日本ではステーキングで得た報酬は雑所得(その他の所得)として課税対象になります。受け取った年の所得として申告が必要で、給与所得などと合算して総合課税されます。金額次第では高額の税率が適用されるケースもあるため、税務面の計算と申告を忘れないようにしましょう(詳細は後述FAQ参照)。
以上のように、ステーキングは「ローリスクで手軽な不労所得」のように語られることもありますが、市場変動やサービス選びなど注意点も多く存在します。メリット・デメリットを正しく理解した上で、自身のリスク許容度に合わせて利用を検討しましょう。
ステーキング報酬も課税対象
仮想通貨ステーキングの始め方ガイド
それでは実際にステーキングを始める手順について、具体的に解説していきます。
大きく分けてステーキングの方法は「自分で公式ウォレット等を使って行う方法」と「暗号資産取引所など第三者のサービスを利用する方法」の2種類があります。
どちらの方法でも基本的な仕組みは同じですが、それぞれに特徴や必要な手順が異なります。以下では両方の方法について、初心者向けにわかりやすくステップごとに説明します。
専用ウォレットでステーキングする方法
1つ目の方法は、公式ウォレットやステーキング対応ウォレットを使って、自分自身でステーキングに参加する方法です。
多くのPoS対応通貨では開発元が公式の専用ウォレット(デスクトップアプリやモバイルアプリ)を提供しており、それを利用することで自分で直接ステーキングできます。例えばカルダノ(ADA)なら「Daedalus」や「Yoroi」といった公式ウォレット、ポルカドット(DOT)なら「Polkawallet」等が該当します。
以下に、ウォレットを使ったステーキング参加の一般的な手順を示します。
- 対象通貨と公式ウォレットの準備
ステーキングしたい仮想通貨を選び、その公式ウォレットまたは信頼できる対応ウォレットを入手・インストールします。ウォレットを初期設定し、復元フレーズや秘密鍵を安全にバックアップしてください(これが資産の命綱です)。 - 取引所からウォレットへ送金
現在取引所にその通貨を保有している場合、ウォレットの受取アドレスへ必要な数量のコインを送金します。送金時にはアドレスの誤入力に十分注意しましょう(一度送金すると取り戻せません)。手数料も考慮して、必要額+αを送ります。 - ステーキングの開始操作
ウォレット内のステーキング機能を利用して、ネットワークへのステーク(委任)を行います。具体的な操作は通貨によって異なりますが、一般にウォレット画面から「バリデーターへ委任する」や「ステーキング開始」といったボタンを押し、委任先ノードを選択・決定します。委任先は信頼性や過去の実績(アップタイムや手数料)を参考に選ぶと良いでしょう。設定を確定するとブロックチェーン上でステーキング処理が行われます。 - ステーキングの維持管理
ステーキング開始後は基本的に放置で構いません。ただしウォレットを削除しないよう注意し、定期的に報酬の受取状況を確認しましょう。通貨によっては一定期間ごとに手動で「報酬の受領」操作が必要な場合もありますが、最近は自動複利的に再ステークされる仕組みも増えています。 - 解除・引き出し
ステーキングをやめたい場合、ウォレットから「アンステーク(解除)」の操作を行います。多くのネットワークでは解除後、資金が自由に使えるようになるまで一定の解禁期間(例:数日〜数週間)が設けられています。解除処理をしてすぐには動かせない点に注意してください。解禁期間が過ぎればウォレット内の残高がロック解除され、再び取引所へ送金したり売却したりできます。
この方法の最大の利点は自分で資産をコントロールできる安心感と対応銘柄の自由度です。
公式ウォレットを用いるため信頼性・安全性が高く、また自分で委任先ノードを選択できるので細かな最適化も可能です。他方、手順がやや専門的で初心者にはハードルに感じる部分もあるでしょう。
ウォレットの秘密鍵管理を誤れば資産を失うリスクも伴います。とはいえ一度慣れてしまえば難しくはなく、資産保護のメリットを踏まえると最も有力な方法と考えられます。
最近では複数通貨に対応した便利な統合型ウォレット(例:Ledger LiveやExodusなど)も登場しています。ただし公式ではないウォレットを使う場合は偽アプリに注意する必要があります。基本的には各プロジェクト公式が案内する方法で進めれば問題ありません。
専用ウォレットを利用するメリット
- 自分自身で仮想通貨を安全に管理することができる
- 多くの場合は公式ウォレットが提供されているため、信頼性・安全性が高い
- 自分で委任先などを選んでより自由にステーキングすることができる
- ステーキング・仮想通貨関連の専門知識が身に付く
- 取引所のハッキング・トラブルなどで資産が引き出せなくなるリスクが少ない
専用ウォレットを利用するデメリット
- ウォレットへの送金・ステーキング手続きなど初心者には難しい手順がある
- ウォレットの秘密鍵・ログインパスなどを忘れた場合には資産を失うことになる
- 仮想通貨を売却する場合などには一度取引所に送金する手間がかかる
- 委任先・ステークプールの選び方によって収益率が下がる可能性がある
- 詐欺ウォレットなどに騙されないよう注意が必要
- ウォレットなどが日本語表示に対応していない場合がある
暗号資産取引所のステーキングサービスを利用する方法
2つ目の方法は、国内外の暗号資産取引所が提供するステーキングサービスを利用する方法です。
対応する取引所に口座を開設し、その取引所内で対象通貨を保有または専用ステーキング商品に預けることで、取引所経由でステーキング報酬を得ることができます。近年、主要な取引所が次々とこのサービスを開始しており、日本国内でもいくつかの取引所で利用可能です。
取引所のサービスは一般に「対象通貨を取引所アカウント内で一定数量以上保有しているだけ」で自動的にステーキングに参加できる仕組みになっており、初心者でも非常に簡単に利用できます。
例えば、国内取引所であるビットフライヤーやコインチェックではリスク(Lisk/LSK)を10枚以上保有しているとステーキング報酬が受け取れる、といった条件があります。必要な保有量は比較的少額に設定されているため、ハードルは高くありません。
以下に、取引所でステーキングを始める一般的な手順を示します。
- ステーキング対応の取引所を選ぶ
利用したい取引所がステーキングサービスを提供しているか確認します。日本国内では後述するように対応数は限られますが、例えばSBI VCトレードやGMOコイン、BITPointなどが主要な提供先です。サービス内容(対応銘柄や利率、条件)を比較し、自分のステーキングしたい通貨に合った取引所を選択しましょう。 - 取引所の口座開設・入金
選んだ取引所で口座開設を行います。本人確認(KYC)手続きを済ませ、取引口座へ日本円や仮想通貨を入金します。すでに口座を持っている場合はこのステップは不要です。 - 対象の仮想通貨を購入または預け入れ
ステーキングを希望する仮想通貨を取引所で購入するか、外部からその通貨を取引所口座に送金します。例えばソラナ(SOL)をステーキングしたいなら、取引所内でSOLを購入するか、自分の他所ウォレットからSOLを入れてください。 - ステーキングの有効化
取引所によっては特別な操作は不要で、保有するだけで自動適用となります(この場合、条件を満たして保有すれば後は待つだけです)。一方、海外取引所や一部サービスではステーキング専用メニューで預け入れ操作が必要な場合もあります。取引所の案内に従い、必要なら対象コインをステーキング用アカウントに振り替えるなどの設定を行ってください。 - 報酬の受け取り
ステーキング開始後、一定の周期(例えば毎日・毎週・毎月)で取引所口座に報酬が配布されます。国内取引所では月次配布が多く、権利確定日時点の平均保有残高に応じて算出されるケースが一般的です。受け取った報酬は取引所の残高に自動反映され、そのまま売却したり再ステーキング(対応していれば)に回したりできます。
取引所経由のメリットは何と言っても手軽さと安全性です。専用ウォレットを用意せずとも取引所の口座さえあればすぐ始められるので、送金ミスなどの心配も減ります。また、国内の大手交換業者であれば金融庁の認可を受けており、厳格なセキュリティや資産管理体制のもとサービスが提供されるため比較的安心感があります。
少額から参加できるのも利点で、例えばSBI VCトレードやGMOコインではETHやSOLを一定量以上保有しているだけで自動的に報酬を得られるため、特別な手続きも不要です。
一方でデメリットもあります。まず、国内取引所の対応銘柄は少ないことです。日本では取り扱い通貨そのものが限定的なうえ、ステーキング対応となるとごく一部に留まります(※後述)。
加えて、取引所は手数料やマージンを差し引いて報酬を分配するため、自己ウォレットで直接ステークするより報酬が少なくなる可能性があります。また、委任先を自分で選ぶことはできず取引所が一括管理するため、細かな運用の自由度はありません。
そして上述のように、ハッキング被害や経営リスクがゼロではない点も頭に入れておくべきです。それでも「自分でウォレットを管理するのは不安」「技術的な作業は避けたい」という方には、取引所のステーキングサービスは最適な選択肢でしょう。日本の初心者ユーザーの多くがまず国内取引所経由でステーキングを体験しています。
なお、海外の大手取引所(BinanceやBybitなど)は対応銘柄が非常に多く報酬利率も高めですが、サイトが日本語非対応だったり利用規約上日本居住者のサービス利用に制限があったりするため注意が必要です。
まずは身近で使いやすい国内サービスから始め、慣れてきたら海外取引所やDeFi(分散型金融)のステーキングにも挑戦すると良いでしょう。
取引所のステーキングサービスのメリット
- 専用ウォレットなどを準備せずに取引所アカウントだけで利用可能
- 仮想通貨の送金・委任などといった難しい操作を行うことなく簡単に始められる
- 送金ミスなどによる資産紛失のリスクを下げることができる
- 取引所によっては複数銘柄のステーキングが可能
- ほぼ放置状態で仮想通貨を増やすことができる
- 仮想通貨を売却したい場合にも送金の手間なくすぐに売却できる
取引所のステーキングサービスのデメリット
- 国内取引所のステーキングサービスは対応銘柄が少ない
- 得られる報酬の額が個人でステーキングした場合よりも少なくなる可能性がある
- 委任先などを自分で指定することができない
- 取引所でハッキングなどの問題が発生した場合には資産流出・出金一時停止などの被害を受ける可能性がある
【2025年版】ステーキングにおすすめの銘柄・サービス
続いて、2025年4時点で特に注目・おすすめのステーキング対応銘柄とサービス(取引所等)を紹介します。
PoSを採用する仮想通貨は年々増えており、主要アルトコインの多くがステーキング可能です。その中でも信頼性が高く人気の銘柄や、高利率が期待できる通貨を把握しておきましょう。また、国内でステーキングを提供している代表的なサービスも合わせて解説します。
ステーキングにおすすめの暗号資産(主な対応銘柄)
- イーサリアム(ETH)
ビットコインに次ぐ時価総額を誇る暗号資産であり、2022年にPoSへ移行したことでステーキング可能になりました。ネットワークの規模が大きく比較的安定した運用が期待できます。年利はおよそ3〜5%前後で推移しており、極端な高利率ではないものの信頼性の高さから人気No.1のステーキング銘柄です。 - ソラナ(Solana/SOL)
高速ブロックチェーンで注目されるSOLもPoSを採用しており、比較的高い年率(6〜8%程度)と成長期待の高さが魅力です。過去にネットワーク障害も報告されましたが改善が進められており、将来性に注目して参加するユーザーも多いです。 - ポルカドット(Polkadot/DOT)
マルチチェーン構想を持つDOTはステーキング利回りが非常に高いことで知られます(10%前後)。その分価格変動も大きいためリスクとリターンのバランスを見極める必要があります。なお、DOTを直接ステークする場合は32DOT以上の自己運用が推奨されていますが、取引所経由なら少量から可能です。 - カルダノ(Cardano/ADA)
日本でも人気の高いADAは、独自のOuroboros PoSにより安定したステーキング運用が可能です。年利は4〜5%程度と中程度ですが、エイダコイン大量保有者が多い日本ではステーキング参加者も多く、信頼性の観点からおすすめできます。特徴としてADAはロック期間なしで自由にステーキング解除可能(いつでも入出金可能)な点が挙げられ、柔軟性を求める人にも適しています。 - コスモス(Cosmos/ATOM)
分散型ネットワークInter-Blockchain Communication (IBC)で知られるATOMも高利回り銘柄です。おおむね7〜10%の報酬が得られますが、やはり価格変動リスクには注意が必要です。 - その他の注目銘柄
テゾス(Tezos/XTZ)は早くからステーキング(ベーキング)を導入した先駆的存在で、6%前後の安定利回りです。シンボル(Symbol/XYM)やクアンタム(QTUM)も日本で取り扱いがあり、ステーキング可能な銘柄として知られます。また、日本発プロジェクトのパレットトークン(PLT)は一時想定年率18%という非常に高い報酬実績もあり話題となりました。高利回りゆえに一定のロック期間が設定されるなど条件がありますが、ハイリスクハイリターンを狙う方には面白い銘柄でしょう。
以上のように、多彩な銘柄がステーキングに対応しています。まずは時価総額が高く実績のあるETHやADA、SOLあたりから始め、慣れてきたらDOTやATOMのような利回り重視の通貨に手を広げるのがおすすめです。
自分が応援したいプロジェクトのコインをステークすれば、利益とプロジェクト支援の両立ができます。「この通貨はステーキングできるのかな?」と思ったら、取引所の案内や公式サイトでPoS採用かどうか確認してみましょう。
ステーキングにおすすめのサービス・取引所(2025年)
続いて、2025年時点で信頼性・利便性に優れたステーキングサービス提供先を紹介します。
日本国内では利用できる取引所が限られますが、その中でも特に評判の良い主要サービスを中心に取り上げます。選定にあたっては「安心して預けられるか」「対応銘柄数や利率は十分か」「使いやすいか」といった観点が重要です。
- BITPoint(ビットポイント)
東証上場企業SBIホールディングス傘下の交換業者で、近年ステーキングサービスに力を入れています。特徴は、国内初となるステーキング報酬の日本円受取サービスを2023年に開始した点です。これによりユーザーは得た報酬をそのまま円換算額で受け取って雑所得として申告でき、時価評価の手間が省けるため税務処理が簡素化されます。
対応銘柄はSOLやXYM、FLRなど比較的新しい通貨も含み、年率も総じて高めです。初心者にも使いやすい画面設計で、SBIグループの信頼感と利回りの高さを兼ね備えたおすすめ取引所です。 - SBI VCトレード
金融大手SBI系列の取引所で、対応ステーキング銘柄数14種類(2025年2月時点国内最多)を誇ります。イーサリアム(ETH)やカルダノ(ADA)、ソラナ(SOL)など主要コインを幅広くカバーしており、対象通貨を口座に預け入れるだけで自動的にステーキング開始となる手軽さが魅力です。
資金のロック期間は設けておらず、途中でもいつでも売却・出金可能なのも安心ポイントです。報酬は毎月10日前後に順次配布されます。運営企業の信頼性が極めて高く、セキュリティ面も万全なことから、安全第一で選ぶなら筆頭候補と言えるでしょう。 - CoinTrade(コイントレード)
やや中堅規模の取引所ですが、イーサリアムのステーキングに国内でいち早く対応したことで注目されています。ETHのほか、PolkadotやNEAR、そして珍しいパレットトークン(PLT)など他では扱っていない高利率銘柄も提供している点が特徴です。得られた報酬を自動で再ステークする設定も可能で、複利運用による効率的な資産増加が期待できます。
ただし、一部サービスでは利用開始時にステーキング利用の申請作業が必要となる場合があります。利用前に公式FAQ等で手順を確認しましょう。尖った銘柄ラインナップが魅力で、上級者にも評価されているサービスです。 - GMOコイン
インターネット大手GMOインターネットグループが運営する取引所で、信頼度と実績は折り紙付きです。ETHやSOL、DOTに加え、国内では珍しいSymbol(XYM)やQTUMのステーキングにも対応し、計9銘柄を提供しています。
特徴として、こちらも資金ロックが無くいつでも売却可能な柔軟性を備えています。報酬は毎月定期配布され、手数料は報酬額の28%が控除(サービス利用料として)されます。またGMOコインではステーキング以外に「貸暗号資産」(レンディング)サービスも展開しており、銘柄によっては貸出の方が年率が高いケースもあります。総合力の高い大手サービスとして、初心者から上級者まで利用者が多いです。
以上が代表的なおすすめサービスです。
これらの他にも、Coincheck(コインチェック)やbitFlyer(ビットフライヤー)といった国内老舗取引所でもLisk (LSK)のステーキングが提供されています。しかし対応銘柄が限られるため、より多様な通貨で運用したい場合は上記のSBI VCトレードやGMOコイン、BITPointなどを検討すると良いでしょう。
なお、海外まで視野を広げるとBinance(バイナンス)など世界最大級の取引所では対応銘柄数・利率ともに群を抜いています。ただし、日本居住者に対するサービスは法規制の関係で制限があるため、利用の際は十分ご注意ください。
まずは国内の公式サービスで経験を積むことを推奨します。その上で、更なる高利回りや幅広い銘柄を求める方は、Lidoなどの分散型ステーキングプールや海外取引所の活用にチャレンジしてみるのも一つの手です(上級者向け)。
最新トレンド・日本における規制状況(2025年)
ステーキングを取り巻く最新動向や、日本国内の規制状況について解説します。2023年以降、業界には大きな変化がありましたが、総じてステーキングは拡大傾向にあります。
グローバルなトレンド・技術動向
イーサリアムのPoS移行と定着
2022年9月の「マージ」完了によりイーサリアムがPoSへ移行し、2023年4月の「上海アップグレード」でステーキングETHの引き出しが解禁されました。この結果、機関投資家も含めた大規模なステーキング参加が進み、ネットワークは安定成長を続けています。
2024年末時点で全ETH供給量の約30%がステーキングされており、PoSの成功例として他プロジェクトへの追随も促しました。今後もイーサリアムでは「ペクトラ(Pektra)」アップグレードなどで効率改善が予定され、ステーキング利回りへの影響が注目されています。
Liquid Staking(流動性ステーキング)の台頭
ステーキングの弱点であるロック期間の拘束を解決する手段として、Liquid Stakingサービスが急成長しました。代表的なLido Financeでは、預けたETHと引き換えに流動性トークン(stETH)が発行され、ユーザーはそれを売買することで事実上いつでも現金化できます。
2025年現在、Liquid StakingはDeFi領域で主要なカテゴリとなり、Lidoはイーサリアム全ステーク量の30%以上を占める最大のバリデータとなっています。分散化や中央集権化リスクの議論はありますが、利便性を高める技術トレンドとして今後も注目でしょう。
主要アルトコインのPoS移行
イーサリアムに続き、他のプラットフォームでもPoS採用が増加しています。例えばPolygon(POL)は独自のPoSチェーンを運用中、Zilliqa(ZIL)やCardano(ADA)は元々PoSで堅調に稼働しています。
またソラナ(SOL)やアバランチ(AVAX)など高性能チェーンが脚光を浴び、ステーキング参加者も増加傾向です。ステーブルコイン運用やDeFi利回り低下の反動もあり、手堅く本家チェーンにステークする動きが広がっています。
日本における規制・市場動向
総じて、2025年現在の日本におけるステーキング環境は安定成長期にあると言えます。主要プレイヤーの参入でサービス品質は向上し、ユーザー数も増加しています。
規制面でも極端な締め付けはなく、むしろ業界と当局が連携しつつ利用者保護と利便性向上を図っている状況です。今後も技術革新やグローバル市場の変化に応じて、新たなチャンスが生まれる可能性もあります。
国内規制当局のスタンス
日本では暗号資産交換業者(取引所)がステーキングサービスを提供する場合、金融庁への登録が必要とされています。現在のところ、ステーキングサービス自体に個別の新規制は設けられていませんが、金融庁は利用者保護の観点からリスク情報の開示を求める姿勢です。
具体的には「随時引き出せない流動性リスク」や「スラッシング等のリスク」について、提供事業者がユーザーに適切に説明する必要があると指摘されています。これは前述のロック期間やペナルティに関する注意喚起で、国内大手取引所では利用規約や説明書に明記されています。
現状、日本においてステーキングサービス自体を禁止・制限するような動きはなく、既存の枠組みで健全に発展させていく方針と読み取れます。
税制面の課題と工夫
ステーキング報酬は雑所得課税となり、計算・申告の手間が指摘されてきました。とくに報酬が暗号資産で支払われる場合、その都度円換算して記録する必要があり、価格変動によっては含み益への課税問題も生じます。この課題に対応すべく、国内ではBITPointの報酬円建て受取サービスのような工夫が始まっています。
さらに2024年度の税制改正では、企業の暗号資産保有に係る期末評価課税の一部緩和などが行われました。個人のステーキング報酬に関しては依然雑所得扱いですが、将来的に申告簡略化や課税方法見直しが検討される可能性もあります。利用者側としては、こまめな記録と必要に応じた税理士等への相談を怠らないようにしましょう。
国内サービスの拡充
日本でもステーキング対応の動きが広がっています。前述のSBI VCトレードやBITPoint参入以外にも、例えばフリマアプリ大手のメルカリ傘下メルコインが2024年末より「メルカリ」でETHを保有するだけで毎月ポイント還元を受けられるサービスを開始しました。これは実質的にメルコイン側でETHをステーキングし、その報酬相当額をユーザーに独自ポイントで付与する仕組みで、暗号資産取引のすそ野拡大を狙った試みです。
他にも、住信SBIネット銀行が預金者向けに暗号資産連動のボーナス提供を検討するなど、伝統金融×ステーキングのような新サービスも噂されています。今後、日本市場でもユーザーの利便性に配慮した独自のステーキング施策が増えていくと期待が寄せられています。
海外動向の影響
海外では2023年にSEC(米国証券取引委員会)が未登録証券の提供として一部の取引所ステーキングサービスに規制強化に乗り出しました。その影響でKrakenが米国でステーキングサービスを停止するといった出来事もありました。
しかし日本においては、ステーキングは基本的に預かり資産の付帯サービスという位置づけで、適切に開示・登録された範囲内であれば問題視されていません。海外の規制リスクが直接国内に波及する可能性は低いですが、グローバル企業の動向次第では日本市場から一部サービスが撤退・変更されるケースも考えられます。
ユーザーとしては国内法に則った事業者を利用する限り大きな心配はいらないものの、ニュースには日頃から注意を払いましょう。
よくある質問(FAQ)
最後に、仮想通貨ステーキングに関して初心者が抱きやすい疑問をQ&A形式でまとめます。
Q:ビットコインはステーキングできますか?
A:
いいえ、ビットコイン(BTC)はステーキングできません。ステーキングはPoSという仕組みを採用する通貨で利用できるサービスであり、ビットコインはPoW(プルーフ・オブ・ワーク)によるマイニングでネットワークが維持されています。そのためBTCを「預けて増やす」仕組みはブロックチェーン上には存在しません。
もしビットコインで利息を得たい場合は、取引所の貸暗号資産(レンディング)など別サービスを利用する形になります。ステーキングとレンディングは混同されがちですが、ステーキング=ブロックチェーン運営への協力報酬、レンディング=第三者への貸出利息と覚えておきましょう。
Q:ステーキング報酬に税金はかかりますか?
A:
はい、かかります。日本国内ではステーキングで得た報酬は雑所得として課税対象になります。受け取った報酬の時価(円換算額)がそのままその年の雑所得の収入額となり、他の所得(給与等)と合算して総合課税されます。
確定申告が必要かどうかは他の副収入も含めた金額次第ですが、原則として20万円超の雑所得が発生した場合には確定申告が必要です。計算方法は、例えば年間で暗号資産の報酬を合計5万円相当受け取った場合、雑所得5万円として扱われ、必要経費(通信費など直接かかった費用)があれば差し引いた額に対して課税されます。
なお、BITPointのように報酬を円建てで直接受け取れるサービスでは、受取時点で円が入金されるためその額を申告すればよく、暗号資産価格の変動を考慮する必要がないメリットがあります。いずれにせよ、ステーキングを行う際は受取履歴を記録しておき、必要に応じて正しく申告しましょう。
Q:ステーキング中の通貨はいつでも売ったり移動したりできますか?
A:
基本的にはできません。ステーキングした暗号資産は多くの場合一定期間ロック(固定)されるため、その間は売買や送金ができません。
例えばPolkadotの場合、解除リクエスト後28日程度の解禁待ち期間があります。ただし、利用するサービスによって異なります。国内のSBI VCトレードやGMOコインではロック期間を設けず、預けたままでもいつでも売却・出金が可能な仕組みを採用しています(その代わり途中で売却した分は報酬対象から外れるなどの調整があります)。
一方、CoinTradeのように高利率の代わりに一定期間引き出し不可といった条件を付けるケースもあります。要は銘柄とサービス次第です。ステーキング開始前に、利用プラットフォームの「利用規約」や「よくある質問」をチェックし、ロックの有無や解除方法を把握しておきましょう。
Q:ステーキングの利率(リターン)はどのくらいですか?
A:
銘柄と市場状況によって大きく異なります。一般的には年利で数%〜10%前後の範囲が多いです。
例えば、主要どころではイーサリアム約4〜5%、カルダノ約4〜5%、ソラナ6〜7%、ポルカドット12%前後、コスモス7〜10%程度…といった目安があります。ただし、これらの数値はネットワーク状況に応じて常に変動しますし、提供する取引所・ウォレットによっても手数料等で実際の受取利率は変わります。
また、一見高利率でも通貨自体の価格下落リスクを考慮しなければなりません。よって、「今この通貨をステーキングすれば年利X%です」という数字はあくまで目安と捉え、鵜呑みにしないことが大切です。最新の利率情報は公式サイトや信頼できる情報源で確認し、現実的な期待値を持って臨みましょう。
Q:少額の資金でもステーキングできますか?
A:
はい、少額からでも可能な場合がほとんどです。多くの取引所サービスでは最低必要枚数が定められていますが、そのハードルは高くありません(例:LSKなら10枚以上など)。
自分で公式ウォレットで行う場合も、技術的には0.1 ADAや1 ATOMといった単位からでもステーク可能です。ただし、ネットワークによって最低委任額が設定されているケースもあります(ETHの自力バリデータは32ETH必要など)。しかしそのETHでさえ、取引所を使えば0.1ETHでもまとめてステークに参加できます。むしろ少額だからこそ、大金を投入する前に試験的に体験してみることをおすすめします。
例えば1万円分ほどの暗号資産をステーキングしてみて、どのくらい増えるのか・どんな仕組みかを実感してみると良いでしょう。専門知識不要で少額から始められるのが取引所ステーキングの魅力でもあります。
ステーキングとレンディングの違いは何ですか?
A:
ステーキングは上述の通りブロックチェーンの取引承認(コンセンサス形成)に協力し、その報酬を得る仕組みです。一方、レンディング(貸暗号資産)は自分の暗号資産を取引所や他のユーザーに一定期間貸し出し、利息を受け取るサービスです。
両者とも「預けて増やす」点は共通しますが、原資が異なると言えます。ステーキング報酬は新規発行コインや手数料収入から支払われ、ネットワーク全体で価値移転が起こります。一方レンディング利息は借り手が支払うもので、いわば借り手から貸し手への価値移転です。
また、ステーキング対象はPoS通貨に限られますが、レンディングはビットコインなどPoW通貨でも可能です。それぞれメリット・デメリットが異なるため、自分の運用方針に合わせて選びましょう。
まとめ
以上、仮想通貨ステーキングについて網羅的に解説しました。
【仮想通貨を安全に長期保有したい方】や【銀行預金より有利な運用を探している方】にとって、ステーキングは非常に魅力的な選択肢です。まずは小さく始めて仕組みに慣れ、徐々に運用額を増やしていくと良いでしょう。
この記事が皆様の参考になれば幸いです。最後に改めて、安全かつ着実な資産運用の一助として仮想通貨のステーキングをぜひ活用してみてください。
こちらの記事も合わせてどうぞ
サムネイル:AIによる生成画像