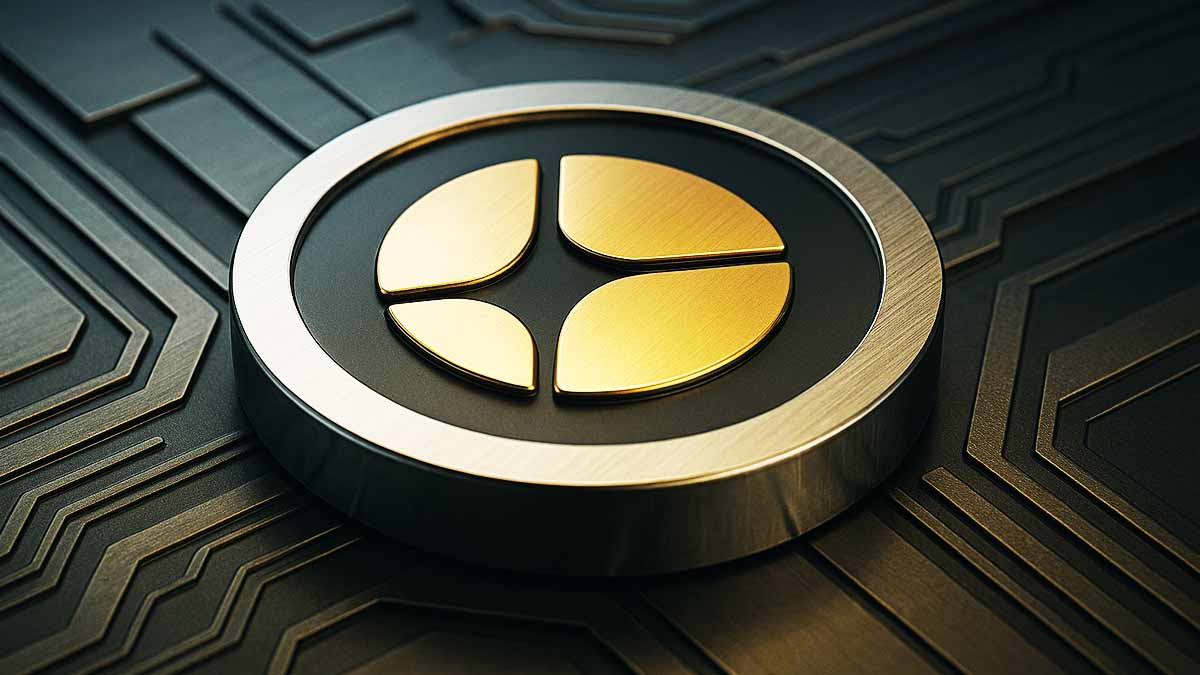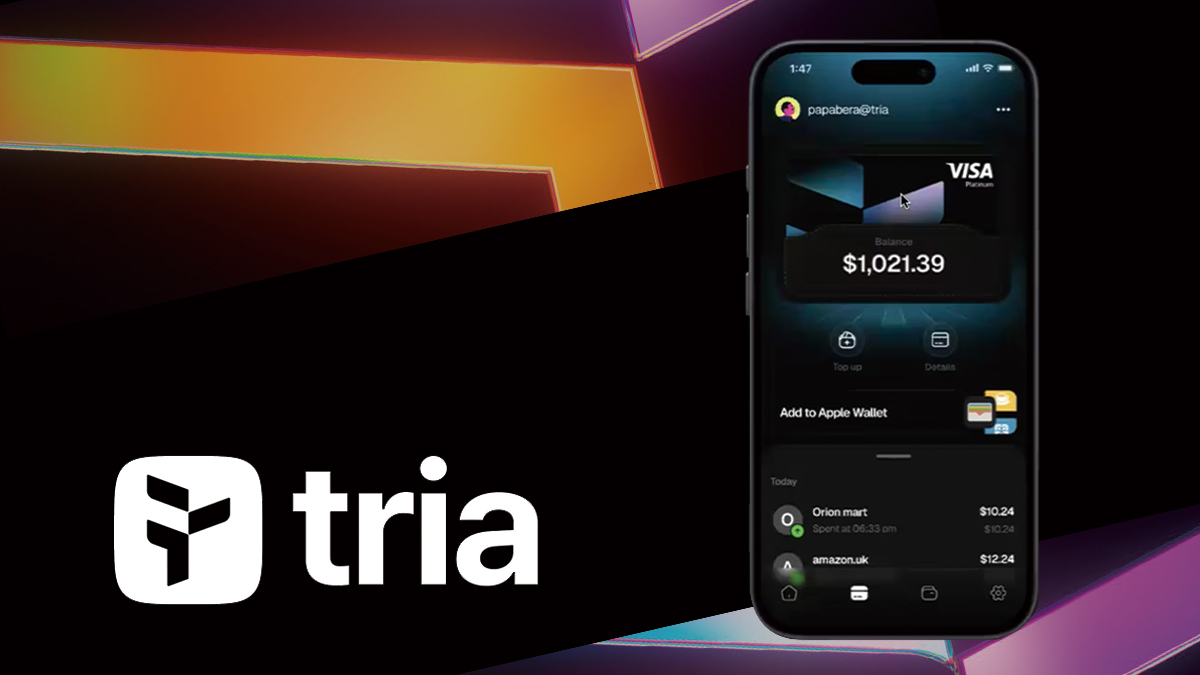ブロックチェーン技術は金融のあり方を大きく変えようとしています。
国際送金の迅速化やコスト削減を可能にするステーブルコイン、既存の金融機関を介さないDeFi(分散型金融)、そして現実の資産をトークン化するRWA(現実世界の資産)など、金融業界全体に革新をもたらしています。
この記事では、ブロックチェーンが金融業界でどのように活用され、実際に何が変わりつつあるのかを、最新事例をもとに分かりやすく解説します。
ブロックチェーンによる金融革命
ブロックチェーンとは、取引データを「ブロック」にまとめて鎖状につなぎ、複数の参加者で共有・管理する分散型台帳技術です。データは一度記録されると改ざんが非常に困難で、システム全体が停止しにくいという特徴があります。
この技術により、インターネット上での取引に第三者の仲介が不要になり、取引の透明性と信頼性が飛躍的に向上します。
ブロックチェーンの導入により、金融業界では従来必要だった銀行や清算機関といった仲介業者を介さずに直接取引が可能になり、コスト削減や取引スピードの向上が期待されています。極端な見方では「銀行が不要になる時代の幕開け」とも言われています。
日本の経済産業省は2016年に「ブロックチェーン技術が影響を及ぼす市場規模は67兆円に達する」との試算もしており、「インターネット以来の技術革新」と期待されています。
金融分野でのブロックチェーン活用例
国際送金を変える仮想通貨決済
【ステーブルコインによる決済】
法定通貨に価値を連動させた仮想通貨「ステーブルコイン」は、値動きの安定性から決済や送金に活用が進んでいます。
米ドル連動のUSDT(テザー)やUSDC(USDコイン)は24時間365日いつでも高速送金が可能で、国際送金の手段としても利用が拡大しています。ステーブルコインが既存の決済ネットワークに匹敵する存在になりつつあることを示しています。
また、大手決済ネットワークのVisaは、自社の決済インフラにUSDCを組み込み、イーサリアム(ETH)やソラナ(SOL)上で決済を実行するパイロットを開始しました。このように、フィンテック企業やカード会社もステーブルコインを活用したリアルタイム送金に乗り出しています。
ステーブルコインの基礎知識
【国際送金の革新】
ブロックチェーンは国際送金(クロスボーダー決済)の効率化でも注目されています。従来はSWIFTネットワーク経由で数日かかっていた海外送金が、ブロックチェーン上の直接取引に置き換われば、数分以内に完了し、手数料も低減することができます。
米リップル(Ripple)社のネットワークを使用した送金では、日本とタイ間の送金時間が従来の数日から数秒に短縮されたケースが報告されています。また、JPモルガン銀行は独自の「JPMコイン」を用いた即時決済ネットワークを構築し、大手銀行間の資金移動をリアルタイム化しています。
さらに、オンライン決済大手PayPal社は、米ドル建ての独自ステーブルコイン(PYUSD)の発行を開始し、大手企業として初めて仮想通貨による送金サービスに踏み出しました。 これは金融テクノロジー業界によるデジタル通貨活用の象徴的な出来事であり、仮想通貨市場が低迷する中でも決済分野での実用化が着実に進んでいることを示しています。
【CBDC(中央銀行デジタル通貨)】
各国の中央銀行も独自の中央銀行デジタル通貨(CBDC)の研究・導入を活発化させています。CBDCは国家が発行する法定デジタル通貨であり、ブロックチェーン技術やそれに類する分散台帳を基盤に設計されます。
既にナイジェリアやバハマなど11か国では、正式にCBDCが発行・流通しており、中国は「デジタル人民元」の大規模パイロットを展開して2億6,000万人が利用可能となっています。
主要国でも、インドやブラジルがデジタル通貨を発行予定で、欧州中央銀行(ECB)はデジタルユーロの導入に向けパイロットを進めています。日本でも日銀が「デジタル円」の検討を開始し、民間企業と協力した技術検証を行っています。
CBDCは国家が保証するデジタルマネーとして、国内決済の効率化や金融包摂の促進が期待されます。一方で、プライバシー保護や既存金融機関への影響など課題もあり、各国で社会実装に向けた議論が続いています。
RWA(現実世界の資産)で進化する金融資産
【STOとデジタル証券】
ブロックチェーンを活用し、現実の資産(株式や債券、不動産など)をデジタル証券としてトークン化するRWA(現実世界の資産)の動きが加速しています。
RWAの代表的な手法であるSTO(セキュリティ・トークン・オファリング)は、ブロックチェーン上でデジタル証券を発行し、資金調達を行う仕組みです。証券の発行・取引・決済までを一貫してブロックチェーン上で完結させることで、中間業者の排除や手続きの迅速化、透明性の向上が期待されています。
香港政府が初のグリーン債券をデジタル発行するなど、公的機関によるRWA活用が世界的に広がりを見せています。
【オンチェーン株式・債券の取引】
証券市場では、オンチェーン化が進み、取引インフラにも大きな変化が生じています。スイス証券取引所「SIX」は、世界初の完全規制下デジタル証券取引所「SDX」を開設し、自社で発行する1億5,000万CHF(スイスフラン)のデジタル債券を発行・上場しました。
日本においても、改正金融商品取引法によりセキュリティトークン(デジタル証券)の法的基盤が整備され、SBI証券や三菱UFJ信託銀行などが不動産ファンドや社債のトークン化を積極的に推進しています。
こうした事例は、ブロックチェーンを用いたRWAの仕組みが、従来の金融市場に確実に組み込まれつつあることを示しています。スマートコントラクトによる自動清算やリアルタイムなデータ共有により、証券取引の透明性・効率性が飛躍的に高まることが期待されています。
RWAの代表格「Ondo
分散型金融(DeFi)による金融サービスの進化
DeFi(分散型金融)とは、ブロックチェーン上に構築された金融サービスのことで、中央の管理者なしにユーザー同士が直接資産を取引・運用できる仕組みです。代表的なDeFiアプリケーションには、分散型取引所(DEX)、分散型レンディング(貸付・借入)プラットフォーム、流動性プールによる資産運用などがあります。
これらはスマートコントラクトと呼ばれる自動契約プログラムで動作し、誰でもインターネット接続があればウォレットを通じて利用可能です。
【分散型取引所(DEX)の台頭】
DEX(分散型取引所)は、ブロックチェーン上で仮想通貨の交換を行う取引所で、中央管理者がいない点が特徴です。
イーサリアム上のDEXであるUniswap(ユニスワップ)は、ユーザーが提供した流動性プールで自動的に売買がマッチングされます。その取引高は既に大手中央集権取引所に匹敵する規模に成長しています。
管理者不在でも信頼性の高い取引サービスが実現できることをDeFiは証明しています。さらに、DEXでは銀行口座を持たない人でも仮想通貨ウォレットさえあれば直接取引に参加できるため、新興国を中心にユーザーが拡大しています。
DEXの基礎知識
【分散型レンディングとイールドファーミング】
「Aave」や「Compound」といった分散型レンディングプロトコルでは、ユーザーが仮想通貨を預けて利息を得たり、担保を差し入れて資産を借りたりすることができます。
スマートコントラクトによって貸し借りが自動執行されるため、信用審査を介さず即座に資金調達が可能です。2021年にはDeFiブームにより預け入れ資産(TVL: Total Value Locked)が急拡大しましたが、その後の市場調整で一時的に減少しました。
現在のDeFiコミュニティでは、高利回りよりもセキュリティや持続可能なユースケースに焦点を移す動きがあり、分散型保険やオンチェーン資産管理など新たな分野への発展が模索されています。
「ブロックチェーン×保険」でコスト削減
保険分野でもブロックチェーンとスマートコントラクトの活用が進みつつあります。スマートコントラクトを使えば、あらかじめ設定した条件が満たされた際に自動で保険金支払いなどを実行できます。
例えば、フライト遅延保険では「フライトが2時間以上遅延した」という情報がオラクル(外部データ連携システム)からブロックチェーン上の契約に提供された瞬間に、保険金支払いが自動実行されます。大手保険会社のAXAは、イーサリアム上でフライト遅延保険「Fizzy」を提供し、遅延発生時にブロックチェーン経由で自動払い戻しする実証を行いました。
特に注目されるのが、発展途上国の小規模農家向け保険など、人手での契約・支払いコストが高い分野でのブロックチェーン活用です。
米保険テック企業Lemonadeはアフリカの農家を対象にブロックチェーンベースの気候保険プログラムを開始しました。
この仕組みでは、天候データに基づく指数保険(パラメトリック保険)が導入されており、干ばつなどの気象条件が一定基準を満たした場合、スマートコントラクトが自動的に保険金を農家に支払います。スマートコントラクトによる自動支払いにより、従来は数ヶ月かかっていた保険金支払いがほぼリアルタイムで完了し、手続きに伴う人件費も削減されています。
また、ブロックチェーンは保険金請求プロセスの透明性向上や不正防止にも貢献します。保険会社間で事故や請求情報を共有するプラットフォームにブロックチェーンを用いることで、二重請求などの不正検知が容易になります。
このように、保険業界では契約執行の自動化とデータ共有基盤としてブロックチェーンを活用し、コスト削減と信頼性向上を図る動きが見られます。
信用スコアは分散型へと進化
【分散型ID(DID)の活用】
ブロックチェーン技術は個人の身元情報管理や信用記録にも応用されています。分散型IDとは、個人が自身の身分証明データを直接管理し、必要な時だけ第三者に提示・検証できる仕組みです。
ブロックチェーン上に本人確認済みの証明書を記録しておき、銀行口座開設時などに利用者がその証明書の存在を証明することで、何度も同じKYC(本人確認)手続きを繰り返す必要を減らせます。
例えばUAE(アラブ首長国連邦)では、企業KYCプラットフォーム「UAE KYC Blockchain Platform」が立ち上げられました。このプラットフォームでは銀行や政府当局が企業のKYC情報をブロックチェーン経由で共有し、新規口座開設時の審査プロセスを簡素化しています。
【ブロックチェーンによる信用スコアリング】
金融履歴を持たない人々への融資や信用供与にもブロックチェーンが活用されています。従来、銀行口座やクレジット履歴がない「アンバンクド(銀行口座を持たない層)」の人々は融資審査が困難でしたが、ブロックチェーン上に取引履歴や返済履歴を記録・蓄積することで、新たな信用評価モデルを構築できます。
例えば米国のスタートアップ企業「Gluwa」は、アフリカなど新興市場の個人ローンの貸出・返済情報を独自ブロックチェーン「Creditcoin」に記録しています。借り手にとっては、地理的な境界を越えて自分の信用を証明できるメリットがあり、貸し手にとっても透明性の高い履歴データに基づきリスク評価が可能になります。
「信用」をブロックチェーン上のデータとして可視化・ポータブル化する試みは始まったばかりですが、これが発展すれば国境や従来の信用情報機関の枠を超えた新しい信用スコアリングの形が生まれる可能性があります。
「ブロックチェーン×金融」が本格化
ブロックチェーンと金融の融合分野では、近年いくつかの重要な動きが見られます。
【大手企業・機関の本格参入】
伝統的な金融機関や大企業がブロックチェーン技術の活用に本格的に乗り出しています。
世界最大の資産運用会社ブラックロックのラリー・フィンクCEOは、株式や債券のトークン化(Tokenization)が資本市場の効率を高め、投資家のコストとアクセスを改善すると述べ、ブロックチェーン技術への期待を表明しました。
また、ナスダックが機関投資家向けのデジタル資産カストディ(保管)サービス開始を表明するなど「トラディショナル金融(TradFi)と仮想通貨の橋渡し」となる取り組みも活発化しています。
【規制環境の整備】
ブロックチェーン金融の最新動向として重要なのが、各国で規制の枠組みが整備されつつあることです。
欧州連合(EU)は2023年に仮想通貨規制の包括法「MiCA」を採択し、ステーブルコイン発行体や仮想通貨サービス事業者に対する明確なルールを定めました。イギリスも仮想通貨規制案を公表し、市場の健全性確保に向けた取り組みを強化しています。
一方、アメリカでは、業界から「ルールの明確化」を求める声が高まっている背景があり、トランプ政権下で法整備が急ピッチで進められています。
日本でも改正資金決済法が成立し、銀行・信託会社によるステーブルコイン発行が解禁されるなど、制度整備が進んでいます。
【市場規模の成長】
世界のブロックチェーン関連市場は年間ベースで高成長を続けています。
データ分析企業「IndustryARC」の予測では、2021年に678億ドルだった市場規模が、2030年には1兆2,357億ドルに達するとされています。
分散型金融(DeFi)の指標であるTVL(預かり資産総額)も、2023年後半から回復基調にあり、ブロックチェーン金融の基盤が着実に拡大していることを示しています。
【金融とブロックチェーンの融合サービス】
最新の動向として、伝統的金融と仮想通貨・ブロックチェーンを組み合わせた新サービスも増えています。
決済大手のVisaが2025年2月に、各種カードで仮想通貨報酬を得られるサービスや、決済ネットワークと仮想通貨ウォレットを直接接続する取り組みを発表しました。
銀行分野では、シンガポールのDBS銀行が許可型ブロックチェーン上で国債をトークン化し、分散型取引所で取引する実証実験に成功したことが報じられています。
日本でもNTTドコモやKDDIなどの複数企業がデジタル通貨やNFTを活用した地域通貨・ポイントサービスの実証を進めています。こうした動きは、ブロックチェーン技術が特別なものではなく日常の金融サービスの一部として溶け込んでいく兆しといえるのかもしれません。
ブロックチェーン金融の展望と課題
ブロックチェーンが金融業界にもたらす今後の展望としては、大きく以下の点が挙げられます。
【規制との両立】
ブロックチェーン金融を発展させるには、規制当局との建設的な連携が不可欠です。マネーロンダリング防止や投資家保護などの観点から適切なルールを設けつつ、技術革新の余地を残すバランスが求められます。
特にステーブルコインやDeFiは国境を越えて利用されるため、各国の規制の足並みを揃える国際協調も課題です。明確なルールが整えば、大手金融機関も安心してブロックチェーン技術を活用できるようになります。一方、規制が不透明な状況が続く地域では、企業の海外流出や影の市場化が懸念されます。
【誰もが金融サービスを利用できるように】
ブロックチェーンは世界中の人々に金融サービスへのアクセスを提供しうる技術です。
現在、世界には17億人もの成人が銀行口座を持たず金融サービスから取り残されていることが報じられていますが、その3分の2は携帯電話を保有しています。スマートフォンとブロックチェーンウォレットがあれば、銀行口座がなくても価値のやり取りや資産の保管が可能です。
ブロックチェーンが普及することで、これまで信用や地理的な理由で金融サービスを利用できなかった層にも、新たな経済機会が生まれる可能性があります。ただし、真の金融包摂を実現するには技術インフラだけでなく、ユーザー教育や詐欺対策も重要です。
テクノロジーに不慣れな人々がデジタルウォレットを安全に使えるよう支援する仕組みや、詐欺的なプロジェクトを見分けるためのリテラシー向上が求められます。
【コスト削減と効率化】
ブロックチェーン導入による金融インフラの効率化は、長期的に大幅なコスト削減をもたらすと期待されています。具体的には、契約書類や決済データの一元管理による照合(マッチング)作業の自動化、決済期間短縮による流動性コスト低減、ミスや重複の削減による事務コスト圧縮などが挙げられます。
特に効果が大きいのはバックオフィス(事務・決済・報告)領域で、データの透明性向上により報告業務コストが大幅に減少するという具体的な試算もあります。これらが実現すれば、金融機関は浮いたコストを新たなサービス開発に回すことができ、利用者も手数料低下など恩恵を受けられる可能性があります。
【透明性と信頼性の向上】
ブロックチェーンの透明な取引記録は「金融の信頼性を高める」と期待されています。不正な取引やデータ改ざんが困難になるため、金融機関内部の不祥事防止や、投資商品における監査の効率化に役立ちます。
証券の取引履歴をブロックチェーンで管理することで、関係当局や投資家はリアルタイムで情報を追跡でき、不正会計やインサイダー取引の兆候を早期に発見できます。また、貸出や与信の履歴が共有台帳に残れば、信用リスクの見積もりが第三者からも検証可能となり、過度なリスクテイクを防ぐ抑止力となります。
透明性の向上はガバナンス強化と腐敗防止に寄与する一方、プライバシーとのバランスも課題です。オープンなブロックチェーン上に機微な金融データを記録することへの懸念から、近年はゼロ知識証明技術などを使ってプライバシーを守りながら取引検証を行う試みも見られています。
まとめ
ブロックチェーン技術は、金融業界におけるインフラそのものを刷新しつつあります。ビットコインに端を発したこの技術は、決済・送金から証券取引、融資、保険、身分証明に至るまで幅広い金融領域で応用が進み、コスト削減やスピード向上、透明性アップといった具体的なメリットを生み出し始めています。
一方で、規制対応やセキュリティ、プライバシー確保といった課題も浮き彫りになっており、技術の進歩と制度整備の両輪で解決が求められます。
ブロックチェーンが金融業界にもたらす変革は始まったばかりですが、そのポテンシャルを最大限に活かしつつリスクを抑える取り組みを続けることで、より安全で効率的でより広く使われる金融システムへの道が開けていくのかもしれません。
ブロックチェーン関連の注目記事はこちら
サムネイル:Shutterstockのライセンス許諾により使用