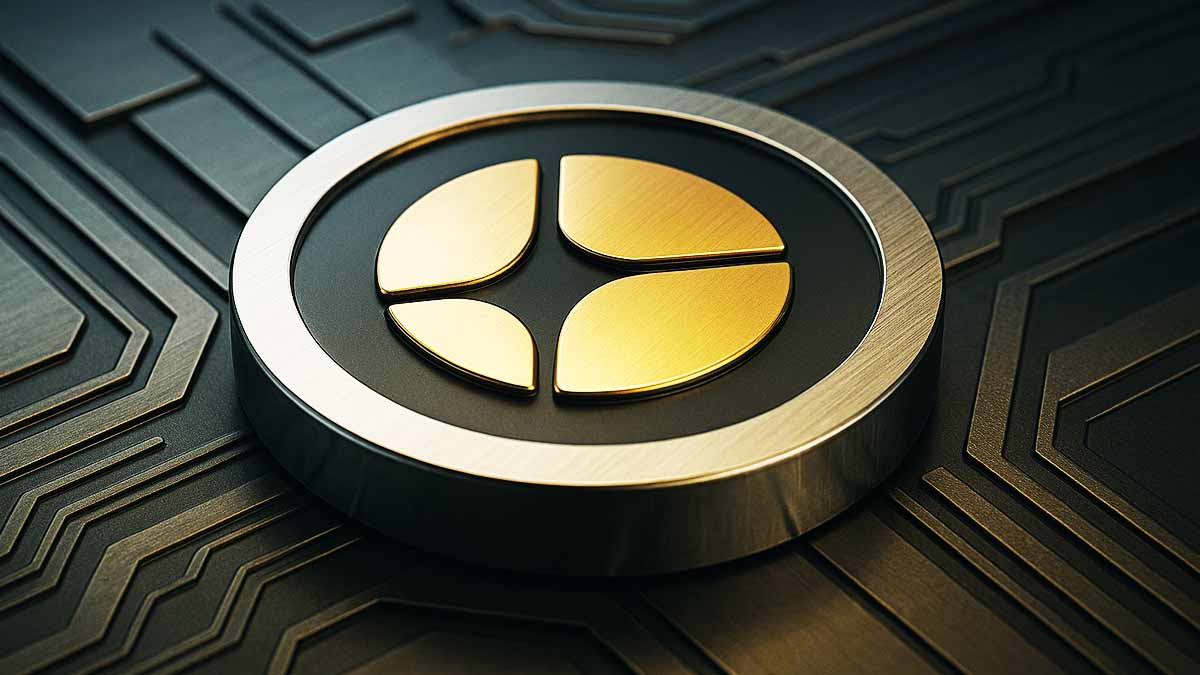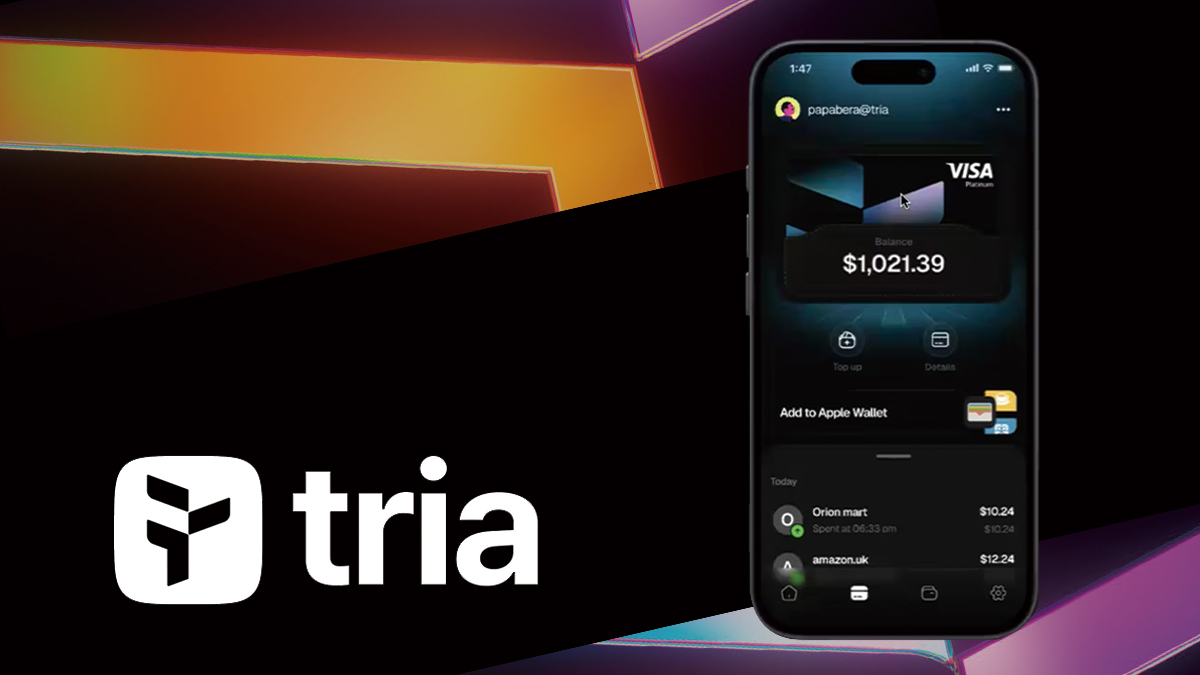仮想通貨市場で近年存在感を増しているのが「ステーブルコイン」です。ステーブルコインとは価格を法定通貨などに連動(ペッグ)させて値動きを安定させた暗号資産のことで、ビットコインなど従来の仮想通貨に比べボラティリティ(価格変動)が小さいよう設計されています。
そのため、仮想通貨初心者でも比較的扱いやすく、暗号資産と現実の通貨を橋渡しする基盤として重要な役割を果たしています。
この記事ではステーブルコインとは何か、その価格安定の仕組みや主な種類、メリットとリスク、代表的な銘柄について初心者向けにわかりやすく解説します。
また、2024年~2025年の最新動向として市場拡大の状況や各国の規制・採用事例もあわせて紹介します。
こちらから読む:仮想通貨関連の基本をわかりやすく解説「初心者向けまとめ記事一覧」
ステーブルコイン(Stable Coin)とは?
ステーブルコイン(Stable Coin)とは、米ドルや日本円などの法定通貨もしくは金などの資産に価値を連動させ、価格の安定性を持たせた仮想通貨(暗号資産)の総称です。
価格変動が激しいビットコイン(BTC)等と異なり、多くのステーブルコインは常に1枚=1米ドル(または1円など)といった安定した価格を維持するよう設計されています。例えば1米ドルにペッグ(連動)されたステーブルコインなら、常に約1ドル前後の価格で推移します。
こうした安定性により、仮想通貨による送金や決済で発生しがちな「送金時と受取時で価格が大きく変わってしまう」リスクを低減できます。
ステーブルコインはデジタル通貨であるため、ブロックチェーンを使った迅速かつ安価な送金手段としても注目されています。従来の銀行送金に比べ、中間手数料を抑えつつ24時間365日リアルタイムで資金移動できる点は大きな利点です。
実際に大手決済会社「Visa」は、ステーブルコインUSDCを活用することで国際送金の決済スピード向上を図るパイロットを開始しており「ソラナ(SOL)などのブロックチェーン上でUSDCのようなステーブルコインを活用することで、クロスボーダー決済の速度向上と資金決済の現代化に役立てている」と述べています。
このようにステーブルコインは既存の法定通貨が持つ「価格の安定性」と、暗号資産が持つ「送金の迅速さ・低コスト」という長所を兼ね備えており、国際送金や決済手段としての利用が拡大しています。
また、多くの暗号資産取引所では基軸通貨(見せ金)としてステーブルコインが採用されており、異なる取引所間で資金を移す際のブリッジ通貨としても広く活用されています。例えばトレーダーは、ボラティリティの高いビットコインを直接移動せず一旦ステーブルコインに換えて送金することで、価格変動リスクを抑えつつ他の取引所へ資金移動できます。
ステーブルコイン(Stable Coin)の分類
ステーブルコインは価格を安定させる方法の違いによって、大きく3つの種類に分類できます。それぞれの仕組みを理解することで、どのように価格安定性が保たれているかが見えてきます。
法定通貨担保型
「法定通貨担保型」は、ドルや円など法定通貨を担保(裏付け資産)として発行されるステーブルコインです。
現在流通するステーブルコインのほとんどがこの方式を採用しており、中でも米ドル連動型が主流です。発行元の企業や団体が、発行したステーブルコインと同等の価値の法定通貨(現金や短期国債など)を準備金として保有することで、常に1コイン=1通貨単位の価値が保証されます。
典型例として挙げられるのがテザー(USDT)やUSDコイン(USDC)などです。これらはそれぞれ発行主体が米ドル建ての資産を準備金として預託することで、ユーザーはいつでも1 USDT、または1 USDCを1 USD相当の法定通貨に交換できるという信用を成り立たせています。
しかし、全ての法定通貨担保型ステーブルコインが完全に1:1で裏付け資産を保有しているとは限らない点に注意が必要です。発行体の財務状況や透明性によっては「本当に発行額と同額の準備金があるのか?」と疑問視されるケースもあり、ステーブルコインの信頼性については議論が続いています。
なお、この法定通貨担保型と同様の仕組みで、金(ゴールド)や原油など商品(コモディティ)価格に連動するステーブルコインも存在します。例えばPax Gold(PAXG)は1コインが1トロイオンスの金価格に連動するステーブルコインで、発行元が実物の金地金を保管することで価値を担保しています。
商品担保型は利用者は少ないものの、法定通貨以外の資産へのペッグというバリエーションもあることを覚えておきましょう。
【法定通貨担保型ステーブルコインの例】
・テザー(Tether/USDT)
・ジェミナイドル(Gemini Dollar/GUSD)
・バイナンスUSD(Binance USD/BUSD)
・トゥルーUSD(TrueUSD/TUSD)
・USDコイン(USD Coin/USDC)
・パクソススタンダード(Paxos Standard/PAX)
暗号資産担保型
「暗号資産担保型」は、その名の通りビットコインやイーサリアム(ETH)などの暗号資産を担保として発行されるステーブルコインです。
基本的な考え方自体は法定通貨担保型と似ていますが、裏付けとなる資産が法定通貨ではなく仮想通貨である点が異なります。ユーザーが担保用の暗号資産を預け入れると、発行プラットフォームから対応する額のステーブルコインが発行されます(いわば暗号資産を担保に借り入れを行うイメージです)。
ただし、担保となる暗号資産は価格変動が大きいため、担保価値が急落するとステーブルコイン自体の価値も維持できなくなる恐れがあります。その対策として、暗号資産担保型ステーブルコインでは通常、発行額を上回る量の担保(オーバーコラテラル)を要求します。
例えば1万円分のステーブルコインを発行するために、2万円分相当のビットコインを担保に預ける、といった具合です。これにより担保価値が半減するような極端な市場変動が起きても、ステーブルコインの価値を下支えできる仕組みになっています。
暗号資産担保型のメリットは、スマートコントラクト(自動契約プログラム)によって発行と担保管理が行われる点です。発行主体の企業に依存せず、プログラム上で担保の預託・清算が担保されるため、ある程度分散型(非中央集権型)の信用を実現できます。
代表例がイーサリアム上で動作するダイ(DAI)で、これは分散型自治組織DAOのMakerDAOによって運営されるステーブルコインです。ユーザーがイーサリアムなどを担保として預け入れることでDAIが発行され、過剰担保と清算システムにより1 DAI ≒ 1 USDの価値維持が図られています。
発行と管理をアルゴリズムとコミュニティ投票で行うため、中央管理者に資産を預ける必要がない点が大きな特徴です。もっとも、暗号資産担保型にも課題はあります。担保として預けた暗号資産の価格が暴落すれば担保不足に陥り、担保清算(強制売却)やステーブルコイン価値の維持に支障をきたす恐れがあります。
また、価格安定の裏付けとして結局は他の暗号資産の価値に依存するため、暗号資産市場全体の信用不安がステーブルコインに波及するリスクも否めません。
実際、主要な暗号資産担保型であるDAIも、その安定維持のために米ドル担保型のUSDCを一部準備資産として組み入れるようになっており、理想的な完全分散型を維持する難しさが指摘されています。
【暗号資産担保型ステーブルコインの例】
・ラップドビットコイン(Wrapped Bitcoin/WBTC)
無担保型
「アルゴリズム型ステーブルコイン(無担保型)」は、法定通貨や暗号資産といった明確な担保資産を持たず、プログラム上のアルゴリズム制御のみで価格を安定させようとするタイプです。
基本的な仕組みとしては、ステーブルコインの価格がペッグ先(例:1 USD)より高騰した場合に新規発行して供給を増やすことで価格を押し下げ、逆に価格が下落した場合には市場からコインを買い戻して焼却(バーン)するか、別のトークンと交換することで供給量を減らし価格を押し上げる、といった操作を行います。
中央銀行が通貨供給量を調節して自国通貨の価値を安定させるような政策を、スマートコントラクトで自動実行しようとする試みであると言えます。しかし、アルゴリズム型ステーブルコインを長期間にわたり安定稼働させることは非常に難しいのが現状です。
理論上は供給量の調整で価格を維持できるはずでも、極端な市場ショックやユーザーの信用低下が起きると、歯止めなく下落してしまうケースが多々ありました。
実際に2022年5月には当時時価総額180億ドルを誇っていたアルゴリズム型ステーブルコインのTerraUSD(UST)が1ドルのペッグを維持できず暴落し、数日で0.35ドルまで急落する事態となりました。
USTの価値安定を支えていた関連トークンLUNAもほぼ無価値になるまで崩壊し、結果的にUSTは市場から消滅しています。この事件はアルゴリズム型ステーブルコインの構造的な脆弱性を浮き彫りにし、市場に大きな衝撃を与えました。
UST以外にも過去にはBasis CashやIronなど複数のアルゴリズム型ステーブルコインが試みられましたが、いずれも長期安定には至っていません。アルゴリズム型では利用者の信頼そのものが価値の支えとなるため、一度信認が崩れると歯止めが利かなくなる傾向があります。
現時点で「これぞ成功例」と呼べる無担保型ステーブルコインは存在せず、アルゴリズム単独で完全な価格安定を実現するのは極めて困難だと言えます。
ステーブルコインのメリット
ステーブルコインが広く利用されるようになった背景には、その実用性の高さがあります。ここでは主なメリットをいくつか挙げます。ステーブルコインは安定性と利便性を兼ね備え、暗号資産エコシステムの中で多方面に活用が広がっています。
価格の安定による利便性
ステーブルコインは価格変動が小さいため、暗号資産同士の交換や商品購入時の支払い手段として利便性が高いです。例えば1 USDCは常に1ドル相当なので、ビットコインのように数十分で何%も価値が変動する心配がありません。
これにより会計管理や価格表示もしやすく、企業が仮想通貨決済を受け入れる際のハードルを下げています。
迅速かつ低コストな送金
ブロックチェーンを利用するステーブルコインは、銀行を介さずに直接価値を送れるため、国際送金や個人間送金を高速・低手数料で行えます。
例えばアメリカから日本へ送金する場合でも、ステーブルコインを使えば数分程度で完了し手数料も数十円程度で済むことがあります(ネットワーク混雑状況によります)。これは従来のSWIFT国際送金(着金まで数日&手数料数千円)と比べ大幅なコスト削減です。
現在では米国大手決済企業のVisaやMastercardもステーブルコインを決済ネットワークに組み込む実験を進めており、決済インフラの効率化につながる技術として期待されています。
取引市場での基軸通貨・流動性確保
仮想通貨取引の世界では、法定通貨の代わりにステーブルコインが基軸通貨(見せ金)として機能しています。
トレーダーはボラティリティを回避したいとき、一時的にビットコインなどを売ってUSDTやUSDCで保有することで、価値をドル建てで安定させることができます。実際、主要取引所ではUSDT建ての取引ペアが多数存在し、ステーブルコインは市場の流動性を支える土台となっています。
ステーブルコインの存在により、暗号資産間の交換や資金待避がスムーズに行えるため、暗号資産市場全体の効率性が向上しています。
金融包摂と価値保存手段
ステーブルコインはインターネット接続さえあれば誰でも利用できるため、従来の銀行口座を持たない人々や、自国通貨の価値が不安定な地域の人々にとって安定した価値保存手段となり得ます。
例えば経済情勢の不安定な国では、自国通貨より米ドルの方が価値保持に信頼がおける場合があります。そのような場合に現地の人々が米ドル連動のステーブルコイン(USDTやUSDCなど)を保有することで、インフレから資産を守ったり、安全に貯蓄したりできるという利点があります。
実際に近年では、南米やアフリカの一部地域で米ドル建てステーブルコインが生活の送金・貯蓄通貨として使われ始めています。
DeFiでの活用と利回り
ステーブルコインはブロックチェーン上のプログラムで扱えるデジタル資産であるため、DeFi(分散型金融)サービスで幅広く利用されています。
例えばステーブルコインを貸し出して利息を得たり、流動性プールに預けて手数料収入を得たりといった運用が可能です。価格が安定している分、他の暗号資産よりリスクを抑えつつ利回りを狙えるため、預金感覚で運用できる点が魅力です。
米ドル預金金利が低い環境でも、ステーブルコインなら年利数%の利回りを提供するサービスもあり、資産運用の新たな選択肢となっています。ただし利回りを提供するDeFiプロトコル自体の信用リスクもあるため、利用時はリスク評価が必要です。
ステーブルコインのリスク・注意点
一方で、ステーブルコインにも押さえておくべきリスクや課題があります。安定を標榜するステーブルコインですが、その信頼性は設計や運用次第で損なわれる可能性があるのです。主なリスクをいくつか解説します。
発行者・裏付け資産の信用リスク
法定通貨担保型ステーブルコインでは、発行元が十分な準備金を管理・維持できるかが信頼の鍵です。
裏付け資産を管理する銀行や発行体企業が経営破綻した場合、ステーブルコインの価値も揺らぎます。2023年3月にはUSDCを発行するサークル社が預けていた銀行(シリコンバレー銀行)が経営破綻し、一時USDCが1ドルのペッグを失って0.87ドル付近まで急落する事態となりました。
米当局の介入で預金保護が確約されたためUSDCはまもなく1ドルに戻りましたが、発行体の財務に問題が生じれば価格乖離(ディペッグ)が起こり得ることが示された例です。また、テザー社のUSDTは過去に準備金の不透明さを指摘されるなど監督当局とのトラブルも経験しています。
このように、ステーブルコインは発行体の信用力や資産健全性に依存している点は大きなリスクと言えます。中央銀行総裁の発言にもあったように「結局ステーブルコインの安定性は発行者のバランスシート次第」である以上、利用者としては発行体の公開する準備金レポートや監査状況に目を配る必要があります。
ペッグ崩壊のリスク(価格変動リスク)
ステーブルコインは常にペッグが維持される保証はなく、極端な事態では急激な価格下落(ペッグ崩壊)が起こり得ます。
特にアルゴリズム型ステーブルコインは前述のように信頼低下で一気に崩壊するリスクが高く、TerraUSD(UST)の崩壊は記憶に新しいところです。
また、法定通貨担保型であっても、上記USDCのように一時的とはいえ0.87ドルまで下落するケースや、2022年にUST崩壊の影響でUSDTが一時0.95ドル前後に下落したケースもありました。
このように市場の極度の不安や流動性不足が生じると「安定」の看板に反して価格が乱高下する可能性があります。ペッグが崩れたステーブルコインは信用を失い、最悪の場合二度と1.0に戻らなくなる恐れもあります。
利用者は各ステーブルコインの過去の安定性実績や、万一ペッグ乖離した場合の清算メカニズム(償還方法)が整備されているかをチェックすることが重要です。
規制リスク(法的リスク)
各国当局は近年ステーブルコインを重要視しており、規制の強化や新法の制定が相次いでいます。そのため法規制による利用制限がリスクとして挙げられます。
実例として、ニューヨーク州金融当局(NYDFS)は2023年2月にバイナンスUSD(BUSD)の発行元であるPaxos社に対し新規発行停止を命じました。この措置によりBUSDの流通残高は急減し、主要取引所からの上場廃止も進むなど事実上の市場撤退に追い込まれています。
SEC(米国証券取引委員会)も一部ステーブルコインを証券と見なす可能性を示唆し発行体を調査するなど、法的な不確実性が高まりました。ただし2025年4月にはSECが「大半のドル連動型ステーブルコインは証券の該当しない」との見解を示し、米国内での法的整理が進む兆しも出ています。
一方、EU(欧州連合)はMiCA規則によって1日あたりの取引量制限や発行者へのライセンス制を導入し、無許可のステーブルコイン流通を禁止する厳格な枠組みを2025年中に施行します。
日本でも2023年に改正資金決済法が施行され、ステーブルコイン発行は銀行など許可事業者に限定されました。
このように各国の規制環境次第では、利用者が今使っているステーブルコインが将来使いづらくなったり、最悪の場合償還(法定通貨への換金)が困難になるリスクも考えられます。常に最新の規制動向に注意を払い、規制面の信頼性が高いステーブルコインを選ぶことも重要です。
証券の定義に該当しない
技術上・運用上のリスク
ステーブルコインもブロックチェーン上に存在する以上、ハッキングや技術的トラブルのリスクがあります。特に分散型のステーブルコインはスマートコントラクトのバグや予期せぬ経済的攻撃(例:担保資産の価格操作)によって破綻する可能性があります。
また中央集権型のステーブルコインでも、発行体のウォレット管理ミスやカストディ業者の事故により準備金にアクセスできなくなる事態もゼロではありません。
さらに、発行体が特定アドレスの資産凍結機能を持つケース(USDTやUSDCは当局要請に応じて特定アドレスの送受信を停止可能)では、資産凍結や検閲のリスクも考慮すべきでしょう。加えて一般の仮想通貨と同様に、ユーザー自身が秘密鍵を紛失すればステーブルコインへのアクセスを永遠に失うリスクもあります。
技術面・運用面のリスクは利用者側の対策(信頼できるサービスを使う、自分で安全に管理する)によってある程度低減できますが「絶対に安心・安全な通貨」は存在しないことを念頭に置き、ステーブルコインも含め暗号資産には常にリスクがつきまとう点を認識しておきましょう。
代表的なステーブルコイン(主要銘柄)
ここでは、市場で特に流通量が大きい代表的なステーブルコインを紹介します。それぞれの特徴を押さえておきましょう。
テザー(Tether/USDT)
テザー(Tether/USDT)は米ドル連動型で、発行主体はTether社(香港拠点の企業)の世界最大のステーブルコインです。2014年に登場した最古参のステーブルコインであり、暗号資産取引所ではUSDT建ての取引ペアが標準的に用いられています。
時価総額は約20兆円(1400億ドル)に達し史上最高を記録しました。USDTは流動性が非常に高く、ビットコインの取引量を凌ぐこともあるマーケットの基軸です。
一方で過去に準備金の透明性が疑問視された歴史があり、2021年には米ニューヨーク司法当局との和解で準備資産の開示や罰金支払いに合意した経緯があります。その後は四半期ごとに準備金レポートを公表し透明性向上に努めていますが、完全な外部監査は未だ実現しておらず、裏付け資産への信頼性が常に議論の的となる銘柄でもあります。
テザー(USDT)をもっと詳しく
USDコイン(USD Coin:USDC)
USDコイン(USD Coin/USDC)は、米国のフィンテック企業サークル社と大手取引所Coinbase(コインベース)社が共同で設立したCentreコンソーシアムによって2018年に発行開始されました。
USDCは常に1:1で米ドルの準備金を保有し、監査法人による月次報告書を公開するなど、高い透明性と規制順守をアピールしています。時価総額は2023年に一時400億ドル超まで拡大しましたが、その後市場要因で減少し、2025年1月時点で約7.7兆円(534億ドル)規模となっています。
USDCは米国の規制下にあることから法令順守面で信頼があり、多くの企業や金融機関との提携実績があります。例えばVisaはUSDCを用いた決済実験を行い、また米大手銀行の一部もUSDCの発行や利用に関心を示しています。
ただし前述の通り、2023年3月には準備金の一部が預けられた銀行の破綻により一時ペッグが動揺する出来事もありました(その際USDC価格は急落しましたが米政府の介入で迅速に回復しました)。
この出来事は規制遵守のUSDCでも想定外のリスクは起こり得ることを示しましたが、同時に透明性の高さから市場の信頼も厚く、現在は安定した運用に戻っています。
ダイ(Dai/DAI)
ダイ(Dai/DAI)は、イーサリアム上で動作する分散型ステーブルコインです。MakerDAOという分散型自治組織によって発行・管理され、暗号資産担保型の仕組みで1 DAI=1 USDの価値維持を目指しています。
2017年に登場し、当初はETHを担保として発行する単一担保型でしたが、現在はBATやWBTC、USDCなど複数の担保資産を受け入れるマルチ担保型へと進化しています。
発行に中央管理者を必要としない完全なオンチェーン運用が特徴で、DeFi(分散型金融)領域では基軸的なステーブルコインとして広く利用されています。
時価総額は約5~6億ドル規模(※2024年時点では約53億ドル)で、USDTやUSDCに次ぐ規模を維持しています。Daiはその非中央集権性ゆえに検閲耐性が高く、自主規制による資産凍結などのリスクが低い点が評価されています。
一方で、前述の通り価値安定のために一部に中央集権型のUSDCを担保に用いるなど、理想と現実の折り合いもつけているプロジェクトです。完全に分散化されたステーブルコインとしては最大の成功例であり、DeFiの発展に貢献しています。
バイナンスUSD(Binance USD/BUSD)
バイナンスUSD(Binance USD/BUSD)は、暗号資産取引所Binance(バイナンス)がブランド展開していた米ドル連動型ステーブルコインです。
発行は米Paxos社(ニューヨーク州規制下の信託会社)が行い、1 BUSD=1 USDを保証していました。かつて時価総額は200億ドル近くに達しUSDCと並ぶ規模でしたが、2023年2月にNYDFSがPaxos社に新規発行停止を命令したことを受け、以降供給量が急減しました。
主要な暗号資産企業の自主規制も相次ぎ、コインベースはBUSDの取引停止、バイナンスも2023年内でのサポート終了を表明しています。
現在BUSDは発行済み分の償還(1:B1でのドル交換)のみ継続され、新規流通は止まっています。このケースは規制当局の判断ひとつでステーブルコイン事業が継続不能になり得ることを示した例として、市場関係者に衝撃を与えました。
その他
上記以外の主なステーブルコインとしては、トゥルーUSD(TUSD)やパックスドル(USDP)、ジェミニドル(GUSD)などドル連動型のものが複数存在します。
また2023年には米決済大手PayPal社が独自の米ドル連動ステーブルコインであるPayPal USD(PYUSD)を発行開始し話題となりました。さらに香港拠点のFirst Digital USD(FDUSD)や、ユーロ連動型のステーブルユーロ(EURS)など、新興の通貨も登場しています。
それぞれ発行主体や仕組みは異なりますが、基本的な目的は「法定通貨価値をブロックチェーン上で表現すること」にあります。今後もユーザーのニーズに応じて様々なステーブルコインが生み出される可能性がありますが、まずは信頼性と実績のある主要銘柄から理解を深めると良いでしょう。
ステーブルコイン市場の最新動向(2024~2025年)
2024年から2025年にかけて、ステーブルコイン市場はさらなる発展を遂げつつあります。市場規模の拡大と規制枠組みの整備、大手企業による採用など、いくつか注目すべきトレンドを押さえておきましょう。
市場規模の拡大と普及進展
2023年後半から暗号資産市場の回復に伴い、ステーブルコインの発行残高も再び増加基調となりました。2025年1月時点で全ステーブルコインの時価総額合計は約2,110億ドル(約30兆円)と過去最高を更新しています。
特にUSDT(テザー)は2023年末に時価総額1,400億ドルを突破し史上最高値を記録しました。USDCも2024年に入ってから再び供給量を増やし、同年1月には約534億ドルに達しています。
市場全体の安定成長により、ステーブルコインは暗号資産全体の時価総額の約15%超を占める規模にまで拡大しました。調査会社Bernsteinは「今後5年でステーブルコイン市場規模は2.8兆ドルに達する可能性がある」との予測を発表しており、金融・消費者向けプラットフォームで本格活用が進めばさらなる成長余地があると見られています。
普及面では、伝統的金融機関や決済企業による活用が進んでいます。2023年には米PayPal社が自社ブランドのステーブルコインPYUSDをイーサリアム上で発行開始し話題となりました。またVisa社はUSDCを用いたクロスボーダー決済の実証実験を拡大し、Solanaブロックチェーン上で高速決済を処理する仕組みを導入しています。
これにより加盟店へのカード決済代金支払いにステーブルコインを直接利用する試みが進められ、既に数百万ドル規模のUSDC決済を処理したと報告されています。さらに銀行によるステーブルコイン参入も現実味を帯びています。
ブラジル最大手のイタウ銀行は2025年4月、独自ステーブルコインの発行を検討していることを明らかにしました。これは国債や不動産といった現実資産(RWA)のトークン化に伴う即時決済手段として、ステーブルコイン活用を視野に入れた動きです。銀行がRWA決済に自社のステーブルコインを用いることで、従来数日かかった証券決済をリアルタイム化する狙いがあります。
日本でも、三井住友フィナンシャルグループ(SMBC)をはじめとする金融機関が2023年にドル建て・円建てステーブルコイン発行のコンソーシアムを組成し、Avalanche等のブロックチェーン技術を活用した実証実験を進めています。
このようにステーブルコインはグローバル企業や銀行にとっても無視できない存在となりつつあり、決済インフラの近代化や資産デジタル化の文脈で採用が拡大しています。
各国の規制動向
ステーブルコインの急成長を受け、各国当局は法整備や規制強化を矢継ぎ早に進めています。
米国では2023年に入って複数のステーブルコイン規制法案が議論され、下院金融サービス委員会でSTABLE法案が可決されるなど進展が見られました。この法案はステーブルコイン発行体に銀行並みの厳格な規制要件や情報開示を課す内容で、健全なステーブルコイン市場育成を目指すものです。
一方でSECは一時、ステーブルコインを証券と見なす可能性に言及して業界に不安を広げましたが、2025年4月にSECスタッフが「多くの米ドル連動型ステーブルコインは証券ではない」との見解を公式に示し、管轄権を主張しない方針が打ち出されました。これはステーブルコインの法的地位に関する不確実性の解消につながる動きで、業界から歓迎されています。
欧州連合(EU)では包括的な暗号資産規制枠組みであるMiCA(暗号資産市場規制)が2023年に成立し、2024年6月からステーブルコイン発行者へのライセンス制や取引上限規制が施行されます。
具体的には、非ユーロ建てのステーブルコインについて1日当たり100万件以上の決済取引を処理することを禁止する条項が盛り込まれており、もし上限を超えるようなら発行者は追加発行やサービス提供の停止を求められる可能性があります。
欧州当局者は「現状ステーブルコイン市場の99%はUSD建てで占められている」と指摘しており、主要なUSDステーブルコイン(USDTやUSDCなど)が欧州市場で活動するにはEUルールへの適合が必須となりました。
このためCoinbaseなど一部の暗号資産事業者は「未認可のステーブルコインは上場廃止も辞さない」と表明し、発行体も欧州向けに体制を整え始めています。
日本では2022年6月に改正資金決済法が成立し、世界に先駆けてステーブルコインの法的位置づけを明確化しました。2023年から施行された新ルールでは、ステーブルコインは「電子決済手段」と定義され、発行できる主体を銀行や信託会社、資金移動業者など登録制の法人に限定しています。
また発行体には1:1の償還請求権を保証することが義務付けられ、利用者はいつでも発行体を通じて日本円など法定通貨への換金が可能です。この枠組みにより、海外発行のUSDTやUSDCも国内で扱う場合はライセンス取得が必要となり、実質的に2023年までは国内取引所でステーブルコインが扱えない状況となっていました。
しかし規制整備を経て、2024年以降は国内企業によるステーブルコイン発行や海外ステーブルコインの正規流通が解禁され、SBIホールディングス傘下のSBI VCトレードが米ドル建てUSDCの取扱いを開始するなど、日本でも徐々にステーブルコイン利用が広がり始めています。
まとめ
ステーブルコインは仮想通貨と法定通貨の架け橋として飛躍的な成長を遂げており、その存在感は金融当局や伝統企業も無視できないものとなっています。
安定した価値と高い利便性から、決済・送金・資産運用など様々な分野で活用が進み、今後も市場規模は拡大が予想されます。一方で、安定性を支える裏付けや規制対応といった課題も浮き彫りになっており、各国でルール作りが急ピッチで進められています。
利用者にとっては、ステーブルコインは非常に便利なツールである反面、その仕組みとリスクを正しく理解し信頼できる銘柄を選ぶことが大切です。仮想通貨初心者の方も、本記事を通じてステーブルコインの基礎知識と最新動向を押さえ、安全で有効に活用していただければ幸いです。
こちらの記事もあわせてどうぞ
サムネイル:Shutterstockのライセンス許諾により使用